日本酒に挑戦してみたけど、なんだかアルコールの味が強くて「おいしい」と感じられなかった経験はありませんか。
もしかしたら、コンビニで手軽に買える「まる」のような、安い日本酒がまずいという体験から、日本酒そのものに苦手意識を持ってしまったのかもしれませんね。
そもそも日本酒はなぜまずいと感じてしまうのか、その日本酒が苦手な理由から、おいしいお酒の簡単な見分け方まで、この記事で詳しく解説していきます。
中には「日本酒にまずい県なんてあるの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、心配はいりません。
うっかり買ってはいけない日本酒を選ばないための知識や、もしもの時にまずい日本酒をおいしくする方法もご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。
 はなまる
はなまる私自身、日本酒が苦手でしたが純米大吟醸を試してからガラリと変わりました。
- 日本酒をまずいと感じる具体的な理由がわかる
- おいしい日本酒とそうでないものの見分け方が身につく
- 初心者が避けるべき日本酒のポイントがわかる
- 苦手な日本酒をおいしく楽しむアレンジ方法がわかる



こんにちは!この記事の著者「はなまる」です。お酒大好きな私が、お気に入りのお酒を紹介します。読者が良いお酒に出会えることを心掛けて記事作成しています。
日本酒がまずいと感じる原因とは


- そもそも日本酒はなぜまずいのか
- 日本酒が苦手な理由3つの特徴
- 安い日本酒がまずいと言われる訳
- コンビニの「まる」はまずいのか
- 日本酒にまずい県は存在するのか
そもそも日本酒はなぜまずいのか
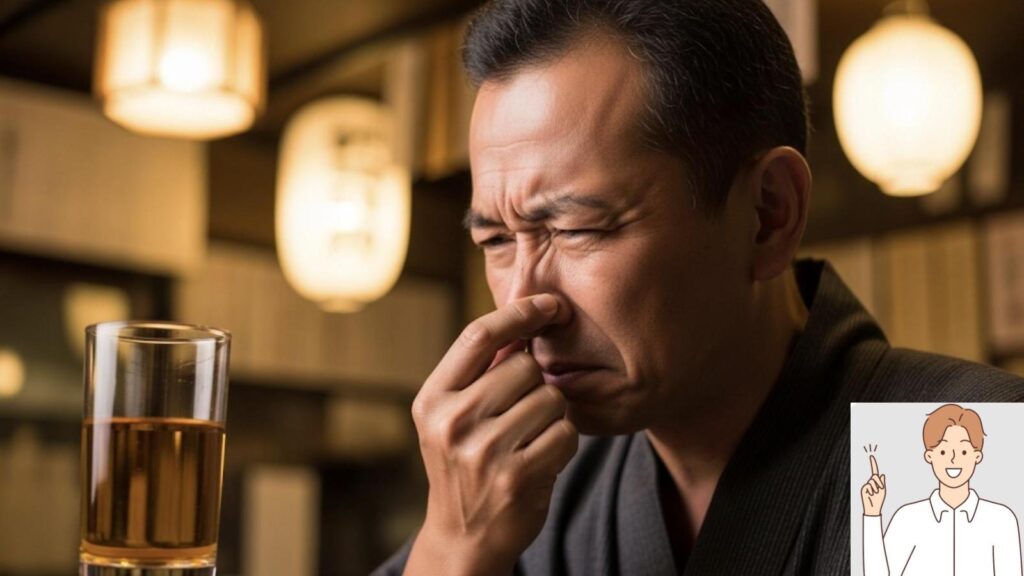
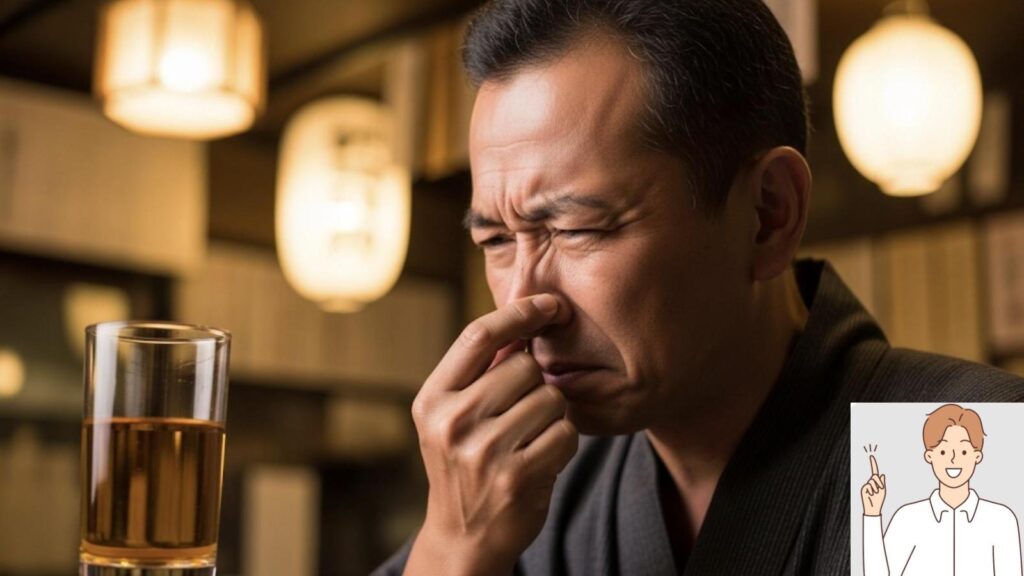
「日本酒はどうしてまずいの?」と疑問に思う方の多くは、日本酒の持つ独特の風味やアルコール感に戸惑っているのかもしれません。その原因は、製造方法と、私たちが普段どんなお酒に親しんでいるかに関係があると考えられます。
言ってしまえば、安価で大量生産される日本酒の多くは、醸造アルコールというアルコールが添加されています。これは戦後の物資不足の時代に、少ないお米でたくさんのお酒を造るために広まった「三倍醸造」という技術が背景にあり、今でもコストを抑える目的で使われることがあります。
この醸造アルコールが、ツンとした刺激や不自然な甘さを生み出し、「日本酒はなんだか飲みにくい」という印象につながっているのです。
また、ワインはブドウの糖分を直接発酵させますが、日本酒はお米のデンプンを麹(こうじ)で糖に変え、それを酵母でアルコールに変える「並行複発酵」という、世界でも珍しい複雑な造り方をします。
このため、アミノ酸などの旨味成分が豊かになり、深みのある味わいが生まれます。しかし、この複雑な味わいが、飲み慣れていない方にとっては「クセが強い」と感じられてしまうこともあるようです。
日本酒が苦手な理由3つの特徴


日本酒が苦手だと感じる方には、共通するいくつかの特徴的な理由が見られます。ここで、主な3つの理由を掘り下げてみましょう。
一つ目は、アルコール感の強さです。一般的な日本酒のアルコール度数は15%前後と、ビール(約5%)や缶チューハイ(5~9%)と比べると高めになっています。そのため、同じ感覚で飲むとアルコールの刺激を強く感じてしまい、「キツいお酒だ」という印象を持ってしまうのです。
二つ目は、独特の香りや甘さです。日本酒には「吟醸香(ぎんじょうか)」と呼ばれるリンゴやバナナのようなフルーティーな香りもあれば、お米由来のふくよかな香り、酵母や麹が醸し出す少しツンとした香りなど、多様な香りがあります。
この香りが体質や好みに合わないと、「酵母臭い」「生臭い」と感じてしまうことがあります。甘みに関しても、お米由来のしっかりとした甘さが、辛口のお酒を好む方には合わない場合があるでしょう。
そして三つ目は、価格と情報の壁です。おいしいと言われる「純米大吟醸酒」などは、四合瓶(720ml)で数千円することも珍しくありません。
ラベルを見ても味の想像がつきにくく、「高かったのに口に合わなかったらどうしよう」という不安から、なかなか手を出しにくいという現実があります。このような理由から、日本酒に対して苦手意識が生まれてしまうと考えられます。
安い日本酒がまずいと言われる訳


「安い日本酒はまずい」というイメージは、多くの方が一度は耳にしたことがあるかもしれません。これは、単なる思い込みではなく、ある程度は製造方法に理由があります。
前述の通り、安価な紙パック酒やカップ酒の多くには、醸造アルコールや糖類、酸味料などが添加されています。これは量を増やして価格を抑えるための工夫なのですが、結果としてお米本来の繊細な風味や旨味が薄れ、不自然な甘さやアルコール臭が際立ってしまうことがあります。これを「お酒風アルコール飲料」と表現する人もいるくらいです。
ただ、ここで誤解してはいけないのは、「醸造アルコールを添加したお酒(アル添酒)が全てまずいわけではない」ということです。「本醸造酒」や「吟醸酒」のように、少量のアルコール添加によって香りを引き立たせたり、味わいをスッキリさせたりする目的で造られる高品質なお酒もたくさんあります。
問題なのは、価格を追求するあまりに過度な添加が行われ、味わいのバランスが崩れてしまった一部の商品です。これらの商品が「安い日本酒」の代表として認識されてしまうため、「安い日本酒=まずい」というイメージが定着してしまったと考えられます。
コンビニの「まる」はまずいのか


コンビニやスーパーでよく見かける「白鶴 まる」。このお酒を飲んで「日本酒はまずい」と感じた、という声は少なくありません。では、「まる」は本当においしくないお酒なのでしょうか。
これを理解する上で大切なのは、「まる」がどのような目的で造られているか、という視点です。言ってしまえば、「まる」は高価な吟醸酒のように繊細な香りや味わいをとことん追求するお酒ではなく、日常の食卓で気軽に、そしてリーズナブルに楽しめる「普段着のお酒」として開発されています。
味わいの特徴としては、醸造アルコールや糖類が添加されており、甘みが強く、やや平坦な印象を受けるかもしれません。日本酒を飲み慣れた方や、繊細な味わいを求める方にとっては、「物足りない」「雑味がある」と感じられる可能性があります。これが、「まる」を飲んで「まずい」と感じる主な理由でしょう。
しかし、一方で「この甘さが好き」「どんな料理にも合わせやすい」と感じる方もいます。味わいの好みは人それぞれですから、「まる」が絶対的にまずいわけではありません。ただ、日本酒の多様な世界の入り口として「まる」だけを体験すると、それが日本酒の全てだと誤解してしまう可能性がある、ということは覚えておくと良いかもしれません。
日本酒にまずい県は存在するのか


「特定の県で造られる日本酒はまずい」という話を聞くことは、まずありません。ですので、「日本酒にまずい県は存在しますか?」という問いへの答えは、「いいえ、存在しません」となります。
日本全国、47都道府県のほぼ全てに酒蔵(さかぐら)が存在し、それぞれの土地の米や水、そして蔵人の情熱によって、個性豊かな「地酒(じざけ)」が造られています。むしろ、地域ごとの気候や食文化に合わせて、驚くほど多様な味わいの日本酒が生まれているのが現状です。
では、なぜ「〇〇県の酒はまずかった」というような個人的な感想が生まれるのでしょうか。その理由は、飲んだお酒がその方の好みに合わなかったか、あるいはその県の日本酒のほんの一部しか代表していない安価な普通酒であった、という可能性が高いです。
例えば、ある県に出張して、居酒屋でたまたま飲んだ安い普通酒が口に合わなかったとしても、それが県全体の酒の評価にはなりません。同じ県内には、素晴らしい純米酒や吟醸酒を造っている蔵がきっと存在します。
したがって、県という大きな括りで味の良し悪しを判断するのは非常にもったいないことです。もし苦手な地酒に出会ってしまったら、それは「そのお酒が合わなかっただけ」と考え、同じ県の別の銘柄や、異なるタイプの日本酒を探してみることをおすすめします。
「日本酒はまずい」を克服する方法


- おいしい日本酒の簡単な見分け方
- 初心者におすすめの日本酒の種類
- スーパーで買ってはいけない日本酒
- まずい日本酒をおいしくする方法
- 日本酒のイメージを変える飲み方
- 「日本酒はまずい」は誤解だった
おいしい日本酒の簡単な見分け方


「まずい日本酒を避けたいけれど、どうやって選べばいいかわからない」という方のために、ここでは簡単な見分け方のポイントをご紹介します。
ラベルの「純米」表記を確認する
最も確実で簡単な方法は、ラベルに「純米(じゅんまい)」と書かれているお酒を選ぶことです。「純米」と表記があるものは、原材料が「米、米こうじ」のみで造られており、醸造アルコールが添加されていません。これにより、お米本来のふくよかな旨味や、蔵ごとの個性を感じやすい傾向にあります。
「純米酒」の他にも、「純米吟醸(じゅんまいぎんじょう)」や「純米大吟醸(じゅんまいだいぎんじょう)」といった種類があります。これらは、よりお米を磨いて雑味を少なくした高級なタイプですが、いずれも「純米」とついていれば、アルコール添加がないお米100%のお酒だと判断できます。
原材料名もチェック
もし「純米」の表記が見当たらない場合は、裏ラベルの「原材料名」をチェックしてみてください。ここに「醸造アルコール」という記載がなければ、それは純米酒と同じです。逆に、この記載があればアルコールが添加されているお酒だと分かります。
まずはこの「純米」かどうか、という点に注目するだけで、日本酒選びの失敗は格段に減るはずです。
初心者におすすめの日本酒の種類
日本酒には様々な種類がありますが、ここでは特に初心者の方が「おいしい」と感じやすい代表的な種類をいくつかご紹介します。好みに合わせて選んでみてくださいね。
| 種類 | 特徴 | こんな方におすすめ |
| 純米大吟醸酒 | 米を50%以上削って造られ、雑味がなくクリア。リンゴやメロンのような華やかでフルーティーな香りが特徴。 | 日本酒のアルコール臭やクセが苦手な方。ワインのように楽しみたい方。 |
| 純米吟醸酒 | 純米大吟醸よりは米の旨味を残しつつ、フルーティーな香りとすっきりした味わいのバランスが良い。 | フルーティーさは欲しいけれど、お米の味もしっかり感じたい方。 |
| 純米酒 | 最もお米の風味や旨味をしっかりと感じられるタイプ。蔵ごとの個性がはっきりと出やすい。 | どっしりとしたお米の旨味やコクを楽しみたい方。燗酒にも向いています。 |
| スパークリング日本酒 | 炭酸ガスを含んだ、爽やかで飲みやすいタイプ。甘口でアルコール度数が低いものが多い。 | 甘いカクテルやシャンパンが好きな方。乾杯のお酒として楽しみたい方。 |



私自身、日本酒が苦手でしたが純米大吟醸を試してからガラリと変わりました。
もし、どれか一つを試すのであれば、多くの方が飲みやすいと感じる「純米吟醸酒」から始めてみるのが良いかもしれません。フルーティーな香りと、お米の優しい甘みのバランスが、日本酒のイメージを良い意味で変えてくれる可能性があります。
スーパーで買ってはいけない日本酒
スーパーは日本酒を気軽に買える便利な場所ですが、選び方を間違えると「まずい」と感じるお酒に当たってしまう可能性もあります。ここでは、特に初心者が避けた方が良い日本酒のポイントをいくつかお伝えします。
製造年月日が古すぎるお酒
日本酒には賞味期限の表示義務はありませんが、瓶には「製造年月日」が記載されています。これはお酒が瓶詰めされた日付のことで、ここから時間が経つほど、光や温度の影響で少しずつ風味が変化(劣化)していきます。特に、吟醸酒のような繊細なタイプは影響を受けやすいです。理想を言えば3ヶ月以内、少なくとも半年以内に製造されたものを選ぶのが無難でしょう。
「大吟醸」なのに安すぎるお酒
「大吟醸」は日本酒の最高ランクですが、大手メーカーから非常に安価な「大吟醸」が販売されていることがあります。これらは規定上は「大吟醸」かもしれませんが、本来の大吟醸が持つ繊細な香りや奥深い味わいとはかけ離れている場合が少なくありません。これを飲んで「大吟醸ってこの程度か」と誤解してしまうのは非常にもったいないことです。
有名銘柄のプレミア価格品
「獺祭(だっさい)」や「久保田(くぼた)」といった有名銘柄が、定価よりもかなり高い値段(プレミア価格)で売られていることがあります。これらのお酒は人気があるため、スーパーでは品質管理が十分でないまま長期間置かれている可能性も否定できません。
高いお金を払ったのに劣化したお酒だった、という事態を避けるためにも、有名銘柄はデパートや正規販売店で購入することをおすすめします。
まずい日本酒をおいしくする方法
もし購入した日本酒が口に合わなかったとしても、諦めるのはまだ早いです。少し工夫するだけで、驚くほど飲みやすく、おいしく変身させることができます。ここでは、ご家庭で簡単に試せる方法をいくつかご紹介します。
温度を変えてみる(お燗・冷酒)
日本酒は「温度で表情が変わるお酒」です。もし常温で飲んで「まずい」と感じたら、温めたり冷やしたりしてみましょう。
- お燗にする: 温めることで、不快なアルコール臭が和らぎ、旨味や甘みが引き立ちます。特に純米酒などは、人肌くらいのぬる燗にすると、味わいがまろやかになります。
- キンキンに冷やす: 冷やすと、香りや甘みが抑えられ、すっきりとした淡白な味わいになります。香りが強すぎると感じたお酒におすすめです。
何かで割ってみる
ストレートで飲みにくい場合は、カクテル感覚で何かと割ってみるのも一つの手です。
- ジュース割り: オレンジやグレープフルーツなど、柑橘系のジュースで割ると、非常に飲みやすいカクテルになります。
- ソーダ割り: トニックウォーターや炭酸水で割ると、爽快感が出てスッキリと飲めます。
- お茶割り: 意外かもしれませんが、緑茶で割ると、お茶の渋みが日本酒の甘みを引き立て、食事にも合わせやすくなります。
しばらく置いてみる
特に「生酒」の場合、開けたてよりも数日〜数週間冷蔵庫で寝かせた方が、味が落ち着いてまろやかになり、好みの味わいに変化することがあります。すぐに飲み切らず、味の変化を楽しんでみるのも面白いですよ。
日本酒のイメージを変える飲み方
「日本酒は和食と一緒にとっくりで飲むもの」というイメージが強いかもしれませんが、もっと自由な発想で楽しむことで、苦手意識を克服できるかもしれません。
一つは、うつわを変えてみることです。例えば、ワイングラスで飲んでみてください。おちょこで飲む時とは違い、グラスの中に香りがこもり、日本酒が持つフルーティーな香りや複雑なアロマをよりはっきりと感じることができます。特に純米吟醸などの香り高いタイプで試すと、その違いに驚くはずです。
もう一つは、意外な料理とのペアリングに挑戦してみることです。例えば、チーズや生ハム、ピザといった洋食と合わせてみましょう。
日本酒の持つアミノ酸の旨味は、乳製品の発酵した旨味や、肉の脂分と非常に相性が良いのです。どっしりとした味わいの純米酒とクリームチーズ、フルーティーな純米吟醸とフルーツの乗ったピザなど、試してみると新しい発見があります。
このように、伝統的な作法にこだわらず、「自分がおいしいと感じるスタイル」を見つけることが、日本酒と仲良くなる一番の近道かもしれません。
「日本酒はまずい」は誤解だった
これまで見てきたように、一口に「日本酒」と言っても、その味わいは千差万別です。もしあなたが「日本酒はまずい」と感じたことがあるのなら、それは日本酒の持つ多様な魅力の、ほんの入り口で少しだけ苦手なタイプに出会ってしまっただけかもしれません。



この記事でご紹介したポイントを参考に、ぜひもう一度、日本酒の世界の扉をノックしてみてください。
- 日本酒がまずい主な原因は安価な普通酒に含まれる添加物
- 「純米」と書かれたお酒は米と米こうじだけで造られている
- 初心者はフルーティーな「純米吟醸」から試すのがおすすめ
- 「まる」に代表される安いお酒は日本酒の全てではない
- 特定の「まずい県」は存在せず、どの地域にも美味しい地酒がある
- おいしい日本酒はラベルの「純米」表記で見分けられる
- スーパーでは製造年月日が新しいものを選ぶ
- 安すぎる「大吟醸」は本来の味と違う可能性があるので注意
- 有名銘柄のプレミア価格品は品質が劣化している恐れも
- まずいと感じたら温めたり冷やしたり温度を変えてみる
- ジュースやソーダ、お茶で割るとカクテル感覚で楽しめる
- ワイングラスで飲むと香りが引き立ち、印象が変わる
- チーズやピザなど意外な洋食との相性も良い
- 固定観念に縛られず自由な飲み方を見つけることが大切
- 「まずい」という最初の体験は、本当においしい一本に出会うためのきっかけに過ぎない
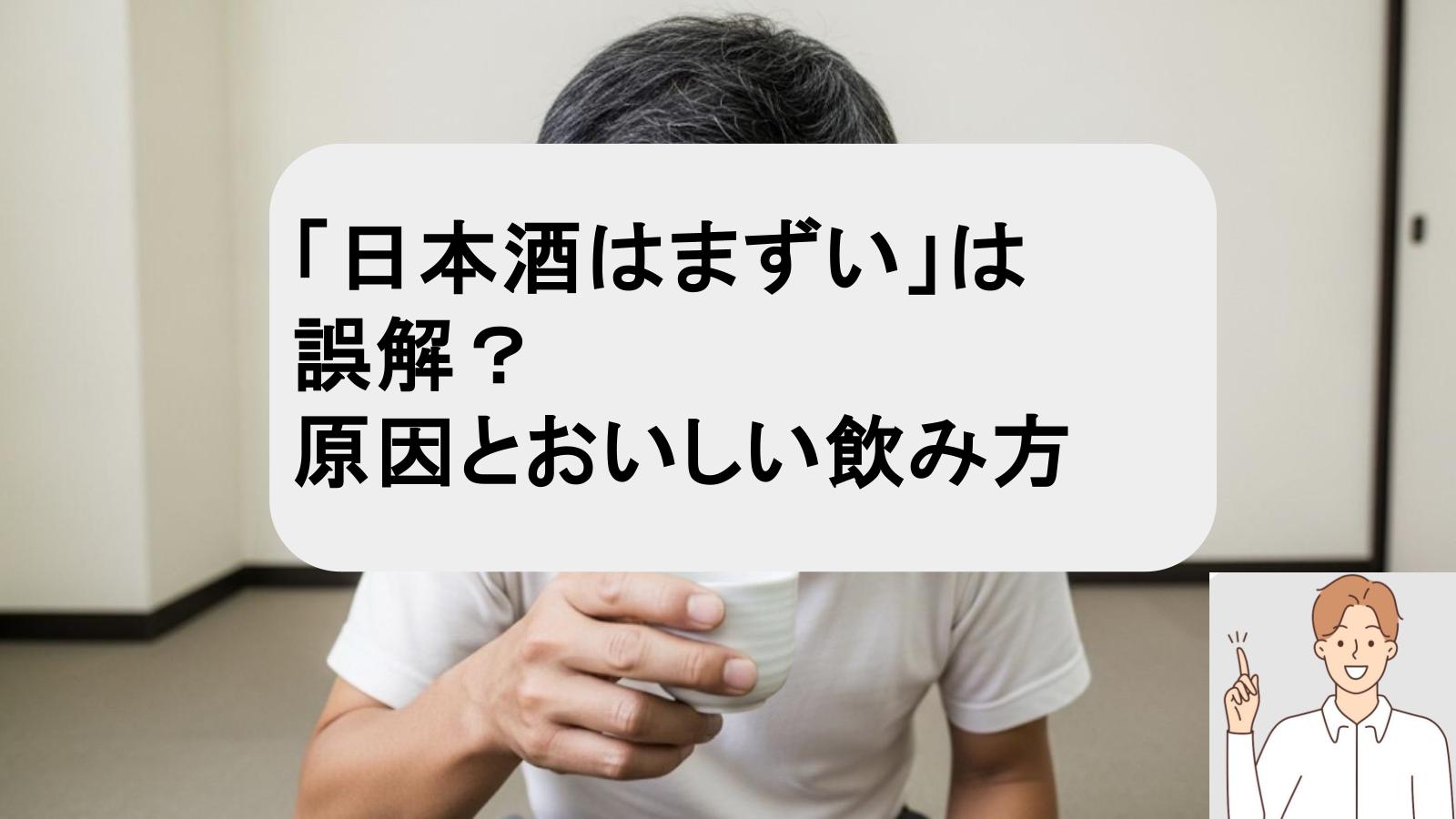
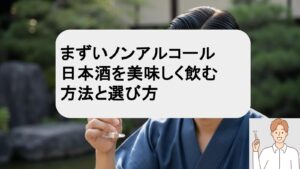
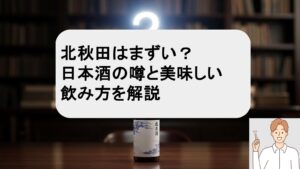

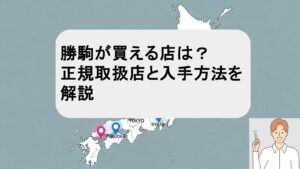
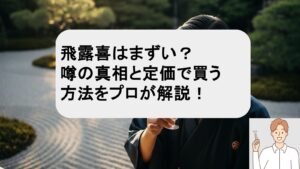
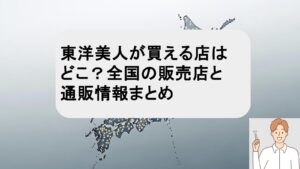
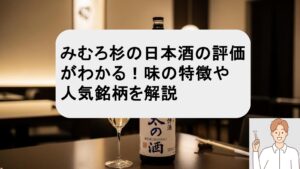

コメント